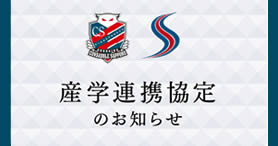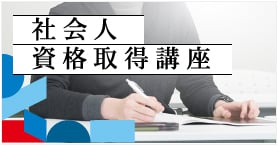2025/10/12 大学より
【生涯学習センター】2025夏秋公開講座「LGBTと私たちの社会」開催


観光学部観光ビジネス学科 斉藤巧弥講師
日々、社会の中で過ごしていると、この分野は積極的に知り取り入れること無しには、まだまだ聴講できる機会も珍しい昨今です。
今回の講義で新しい学びを期待して、また人に寄り添える知識を得るために、もしくは様々な場面で「ハラスメント」を指摘される昨今の社会において、知らぬでは済まされないという世の流れを感じて受講される方など、様々な思いで受講者は集まった模様です。
第1回:性の多様性の基礎知識

第1回目は、性は多様であること、周囲と折り合いながら生きる少数の人(以降「当事者」)がいることを認識し、その置かれた現状を学びました。
講師からは多種多様な性の区別を主たる要素に分けて丁寧に説明を受け、その上で一般人の性的マイノリティへの印象や、各当事者のカミングアウト状況等について、統計資料等を元に展開されました。
特に後半で語られた話題はどの受講生にとっても心に残る内容ではなかったでしょうか。社会で生き難さを感じながらも、周囲に対して配慮するために日々の困難さも自分なりに対処される当事者の姿と、このことが表面化されることがないため、他人に気が付かれることも無いという実情。当事者の置かれた事情を知った受講者には衝撃的な感情がよぎったことでしょう。
「何かできることはあるのか?」という受講生の問いに、講師からは「多様な性があることを理解し、何かできることがあるだろうかという意識を持つことこそ、何らかの対応が生じた時に生きてくるのではないか」と応じられました。
第2回:札幌から世界までー多様な性と私たちの社会
国や地域の習慣や文化的背景から派生する不理解、また無理解な政治家の発言や国の政策決定は、当事者が望
む社会をいっそう遠のかせます。規範的とされる性のあり方以外を認めず国の法令で罰則を設けている国もあれば、
医学的な配慮により当事者保護の政策を設けていた国であっても、無理解な政治家の考えで政策が変わりつつある
国もあります。その一方で、法整備が進み同性婚が可能となった国もあります。
当事者への対応は各国様々に違います。ですが、人びとの多様な性のあり方を受入れて法整備が進んだ国は、
大多数の人と少数派の性を持つ人がお互い平等を感じられる社会になっているか言うと、必ずしも比例するとは
限らないことを講師は統計資料を示した上で説明されました。法が整っていたとしても、LGBTQの当事者を過ご
しやすい社会環境に置いてくれる訳ではないそうです。
中盤ではLGBTQに関する取り組み、イベントの由来や社会運動「プライドパレード」を、後半は日本の状況について語られました。特に学校への対応は教育現場での差別をなくすために急務です。国による学校での状況調査と実施対策、現場での対応例による指南はされているものの、LGBTQについては学びの取り組みが進んでいない
状況にあることも示されました。
前述で「聴講できる機会も珍しい昨今」としましたが、その通りで、教育現場では講師の担い手や扱う方針も含めて拡充はこれから進められていくそうです。とは言え、ごく最近の小学校の検定教科書の中にもLGBTQに関する説明が掲載されている内容も増えてきており、若い人ほど認知されていく将来が見えました。
最後に、札幌で利用できる行政サービス、北海道での同性パートナーシップ制度状況と全国における登録件数の変化、市内企業を対象とした登録制度「札幌市LGBTフレンドリー指標制度」などが紹介されました。
質疑応答では教育現場の学びの広まりについての問いに、講師からは先進的な学びとして高校生が自主課題として学んでいる事例が伝えられました。
性が多様であると知り、理解することから生まれる私たちの意識が、少数派の性をもつ人々との互いの過ごしやすさに繋がれば、という思いがこの講座開講の主旨でありました。受講された皆さん、いかがでしたか。